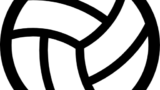引用元:時事通信
「東洋の魔女」と最初に呼んだのは、ソ連の新聞だったという。1962年に世界選手権初優勝を遂げ、64年東京五輪で期待通り金メダルを獲得した日本女子バレーボール。人々は回転レシーブに目を見張った。
相手の打球に飛び込んでパスを上げ、床に転がるとすぐに立って攻撃の体勢を取る。61年初め、大松博文監督がイメージを口にすると、河西(のち中村)昌枝主将は「そんなこと…」と返したが、「できんことをするんが練習や」と大松監督。
監督が次々と打つボールを、選手が転げ回って拾う。けがが続発し、腫れた背中に職場の座布団を巻き付けて練習する選手もいた。
長時間の苛烈な練習は、非合理的とも批判され、柔道の受け身を習得してからやるべきだとの声もあったが、大松監督は「柔道は回って立つだけ」と退けたという。
後になって身のこなしや技術、筋力、持久力、精神力を一度に鍛える特訓は合理的だとさえ言われたが、監督自身は非合理的だと分かっていた。
背景には、9人制から6人制への移行がソ連、欧州などから大きく遅れていた日本バレー界の事情がある。
大松監督は守備に危機感を抱いた。体格差は攻撃に表れると思われがちだが、バレーはボールを床に落とさないことが大前提。9人制と同じコートを6人でカバーするのに、小柄で手足の短い日本選手は不利だった。
そこから回転レシーブの発想が生まれ、完成を急ぐには手順を踏む時間がなかったが、選手たちの血みどろの努力が可能にした。「1日1000本は上げたかな。コートの中ではみんな、女じゃなかったから」。河西は生前、朗らかに笑った。